「川越の街は”建物”に注目するともっと楽しめるんです。」
穏やかな語り口で、そう話すのは川越市出身の出版社「仙波書房」代表・神谷さん。
かつては大手出版社で営業職として働きながら、数字と向き合う日々を過ごしていた。
しかし父の死、そして自身の人生を見つめ直す時間を経て、2021年、神谷さんは小さな出版社を立ち上げた。
そこから始まったのは、華やかではないけれど、街と人の記憶を未来につなぐ挑戦だった。
Contents
■ 出版社という“数字の世界”から、まちの声を拾う仕事へ
「最初に勤めた出版社では、営業の代表を務めていました。取次店や書店を回りながら、本の売上や在庫を“勘”ではなく数値で管理しようと提案したんです。」
当時はまだアナログな時代。売上や在庫の感覚が曖昧なままに判断されることも多かった。
そんな中で神谷さんは、データ化や分析を自ら進め、出版の現場を見える化していった。
「営業だけでなく、編集の仕事も理解しろと言われまして。編集マニュアルを作るように上司から言われたんです。でも当時、編集の経験なんてゼロ。そこから編集者たちに頭を下げて、仕事の流れを一から学びました。」
営業、編集、制作。出版の全工程を横断的に経験したことで、やがて神谷さんの中に“いつか自分で本をつくりたい”という思いが芽生え始める。
■ 父の死と離婚──「定年を待ってからでは遅い」と気づいた瞬間
転機は突然やってきた。
医学書出版社に勤め、全国の学会や販売会を飛び回っていたある日、父が倒れたとの知らせが入る。
「父はずっと元気だったんですが、突然のがんの診断。あっという間に入院して、1ヶ月も経たないうちに亡くなりました。」
家族性のがんの可能性を医師から聞かされ、神谷さんは「自分もいつ同じようになるか分からない」と強く感じたという。
ちょうどその時期、離婚も経験し、一人になった。
「もし定年まで会社員を続けたら、出版社をつくるのは70歳を過ぎてからになる。
でも、それでは遅い。時間は有限なんだと気づいたんです。」
そして2021年。コロナ禍真っ只中、神谷さんは自らの手で「仙波書房」を立ち上げた。
■ コロナ禍の逆風、そして“地元”という原点への回帰
独立当初、神谷さんは医療系の問題集・参考書を出す予定だった。
しかし、思わぬ壁が立ちはだかる。大学や病院が閉鎖的になり、取材や営業が一切できなくなってしまったのだ。
「医療系の本づくりは難しいと判断しました。その時に頭に浮かんだのが、“地元・川越”というテーマです。」
実は神谷さん、子どものころから建物の模型づくりが趣味だった。
街歩きの途中で気になった蔵や町家をスケッチし、細部まで再現する。そんな活動を続けていた。
「模型をつくるときに、どうしたら建物の魅力が伝わるかを本気で考えてきたんです。
その経験を“本”という形で表現したら面白いんじゃないかと思いました。」
こうして生まれたのが、『川越の建物 近代建築編』『川越の建物 蔵づくり編』の2冊である。
■ “女性の感性”を装丁に取り入れる出版のかたち
仙波書房の本を手に取ると、まず感じるのはその心地よい質感だ。
表紙はマットコート仕上げで、すべすべとした手触り。
タイトルの文字も、柔らかい印象の線で構成されている。
「読者ヒアリングをした中で、ある女性の方が“化粧品の箱の手触りが好き”と言っていたんです。
その言葉を聞いて、“本も触っていたくなるような質感にしたい”と思いました。」
さらに、表紙デザインにも工夫がある。
当初は“建物の重厚さ”をイメージして太字のゴシック体を使っていたが、「女性は手に取らないかもしれない」との意見を受けて、より軽やかなフォントに変更した。
「装丁って、ただの見た目ではなく“入口”なんです。
誰にとっても開かれた本にしたかった。」
■ アニメ制作会社との異色コラボレーション
『川越の建物 近代建築編』の扉絵には、美しいアニメ調の背景イラストが描かれている。
これは、アニメーション背景制作会社「プロダクション・アイ」とのコラボレーションによるものだ。
「“建物に興味がない人でも手に取ってもらうにはどうすればいいか”を考えたとき、
“アニメのような世界観で見せたら?”という意見が出たんです。」
そこで神谷さんは、実際にアニメ制作会社に相談。
すると、「どうせやるなら本格的な背景制作会社と組んだ方が面白い」との提案を受け、コラボが実現した。
「川越が舞台のアニメ作品『月がきれい』のように、街そのものが“舞台”になる。
そんな一冊をつくりたかったんです。」
■ 取材先との出会い、そして届いた「手紙」
取材は常に地道で、時に厳しい。
初めて蔵造りの職人を取材したときは、2時間話を聞いても半分も理解できなかったという。
「何を言っているのか分からない。でも、分からないからこそ徹底的に調べる。
その繰り返しでした。」
後日、取材した建物オーナーから分厚い封筒が届いた。
恐る恐る開けると、そこには感謝の言葉が並んでいた。
「“今までいろんな本で紹介されたけど、ここまで丁寧に調べてくれたのは初めてだ”と書かれていました。
涙が出るほど嬉しかったですね。」
■ “街の記憶”を未来へつなぐ出版へ
現在、神谷さんは第3弾となる『歴史探求 川越の妖怪・物の怪話』の制作を進めている。
さらにカルチャーセンターでの講座や街歩きツアー、建物模型の展示など、活動の幅を広げている。
「出版は、単なるビジネスではなく“記録と継承”の仕事です。
川越の建物や文化、そしてそこに関わる人たちの想いを、次の世代に伝えていきたい。」
静かに、しかし確かな情熱を持って。
仙波書房は今日も、川越の街のどこかで新しいページをめくっている。

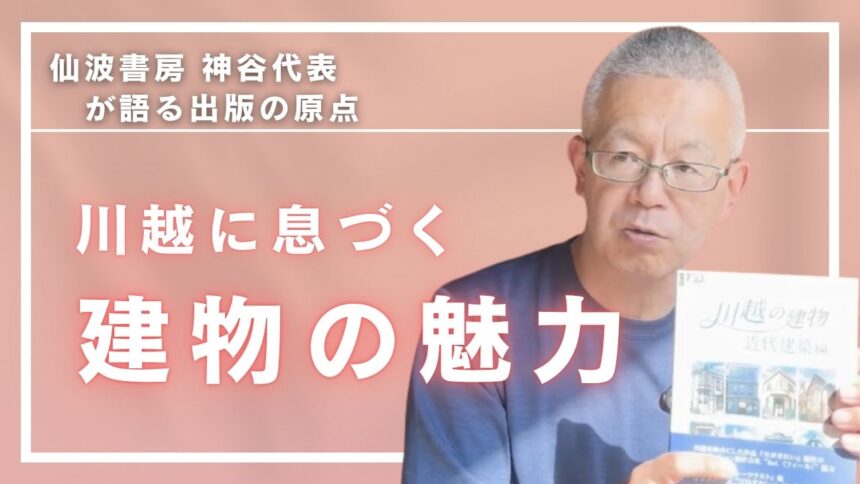

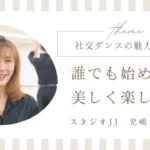
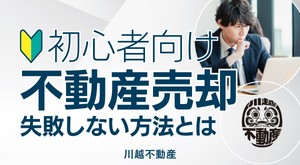


この記事へのコメントはありません。